私の工房のそばには宇治川が流れていて、その河原は一面の芒 (すすき) が茂っている。そこには観月橋がかかっていて、まさに月の名所であった。とくに桃山時代、豊臣秀吉は近くの伏見山に城を築いたが、この川のほとりに出て、名月を鑑賞したといわれている。今は国道二十四号線がそこに走っていて、そうした昔の風情はないけれども、東の宇治、木幡山あたりから出る月は美しく、河原の芒がそれに添うように秋風にゆれている。
今日、九月二十日は中秋の名月である。空が澄んで美しい月が見られる。十五夜でなくても、満ち欠けがあっても、秋の夜、月をめでるのは心がやすまる思いがする。
日本では月には必ず「すすき」が添えてある。とりわけ江戸時代の絵画、たとえば武蔵野図などには月と細やかな流麗な線で芒の葉が数えきれないほど画面一面に描き込まれている。
そのような意匠は絵画だけでなく、金蒔絵、陶芸そして染織品、とりわけ能装束に多く取り入れられてきた。
暑い夏がすぎて、ようやく心地よい季節になったころ、秋の七草そして菊、紅葉と昔から移りゆく秋色を楽しんできたのである。
やはり日本の秋のよさは、ゆっくりと色が移ろっていくことである。
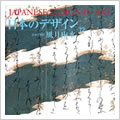 『日本のデザイン12: 風月山水草』
『日本のデザイン12: 風月山水草』
吉岡幸雄 (編集)
紫紅社刊




